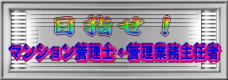
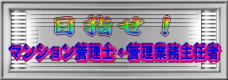
平成28年(2016年) 管理業務主任者 試験問題 及び 解説
ページ1(問1より問25まで)
 次へ
次へ※ ・マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示第490号)及びマンション標準管理規約は、平成28年3月に改正があったので注意のこと。
・マンション標準管理委託契約書は、平成28年7月に改正があり、平成29年度の試験から出題適用となるので注意のこと。
マンション標準管理規約は、平成16年に改正があった。また、平成23年7月にも小幅な改正があった。
マンション標準管理委託契約書は、平成15年に改正があった。また、平成22年5月にも改正があった。
|
[問 1] 被保佐人が所有するマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売却に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。 建物の区分所有等に関する法律(以下、当解説では、「区分所有法」といいます)では、法律用語として「マンション」の定義がありません。しかし、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、当解説では、「マンション管理適正化法」といいます)第2条では、以下のように定義されていますので、マンションの用語を試験で使用する際には設問のような「マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう」の表現が使用されます。 |
| 問2 |
|
[問 2] マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)の管理者B(以下、本問において「B」という。)が、その職務に関し、C会社(以下、本問において「C」という。)との間で取引行為(以下、本問において「本件取引行為」という。)をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
| 問3 |
|
[問 3] 消滅時効及び除斥期間に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 |
|
[問 4] 甲マンションの一住戸乙(以下、本問において「乙」という。)を数人が共有する場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
|
| 問5 |
|
[問 5] マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)は、敷地に集会棟を新築する工事(以下、本問において「本件工事」という。)を行うため、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間で請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
|
| 問6 |
|
[問 6] マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の区分所有者A(以下、本問において「A」という。)の死亡により、法定相続人であるBとCが甲を相続分2分の1ずつで共同相続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
|
|
*注:マンション標準管理委託契約書は、平成28年7月29日付で、14条が改正されているので、平成29年の受験生はしっかり、改正箇所に注意のこと。 [問 7] 次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、「標準管理委託契約書」という。)によれば、最も適切なものはどれか。
|
|
*注:マンション標準管理委託契約書は、平成28年7月29日付で、14条が改正されているので、平成29年の受験生はしっかり、改正箇所に注意のこと。 [問 8] 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものの組み合わせはどれか。 |
|
*注:マンション標準管理委託契約書は、平成28年7月29日付で、14条が改正されているので、平成29年の受験生はしっかり、改正箇所に注意のこと。 [問 9] 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。 |
|
[問 10] マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
|
[問 11] マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
|
[問 12] 建物の建替えに係る経費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号、国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下、「標準管理規約」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。
|
|
*当問題の解説は、高井憲彦様のご協力によるものです。高井様、ありがとうございます。 [問 13] 管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。 |
|
[問 14] 管理組合の活動における以下の取引に関して、平成28年3月分の仕訳として最も適切なものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。
*私の過去問題の解説を読んでいる人には、度々の重なる説明で恐縮ですが、マンションの管理組合では、明確な会計基準がありません。
管理業務主任者試験においては、例年2問、仕訳の出題があります。2問を落とすと全体の得点に大きく響きますよ!
・内訳は
③4月分の駐車場使用料 が 850,000円 これは、4月分で 3月の仕訳では、まだ発生していないため、翌年度の収入の 前受金(負債勘定)の増加として、 貸方へ 850,000円を記帳します。
④新規契約分敷金 が 50,000円 ここで、敷金の性格はどうかをきいています。 通常、敷金は、駐車場契約の終了時に契約者へ返還される性格だと判断して、ここでは、預り金(負債勘定)の増加とし、貸方へ 50,000円を記帳します。
⑤ここで、注意が必要なのが、取引の文中にある、「なお、3月分駐車場使用料のうち 20,000円については、3月末現在、入金されていない」です。 出題傾向として、必ず、うっかりしやすい本文にこのような記述を潜ませますので、注意してください。 3月分駐車場使用料のうち 20,000円については、3月末現在、入金されていないなら、これも発生主義の原則により、駐車場使用収入 として、貸方に記帳します。 しかし、相手科目は、まだ、収入がないので、未収入金 とします。
最後に、貸方の駐車場使用収入 の 100,000円 と 20,000円 合計 120,000円 をまとめると、
となり、答えは 1 です。 答え:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[問 15] 管理組合の活動における以下の取引に関して、平成28年3月分の仕訳として最も適切なものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。
イ.しかし、支払は、3月には、していないにより、 貸方に 未払金 で記帳しますが、金額については、もう既に2月に、着手金として、前払金で 500,000円を処理したことを思い出してください。
となり、答えは、4 です。 答え:4 《タグ》会計。仕訳。勘定科目の選択。建物。修繕費。未払金。前払金。 ここも、勘定科目の選択で建物か修繕費かが少し悩むが、難しくはない。 |
| [問 16] 管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 法人税法上、人格のない社団である管理組合においても、組合員から徴収する専用使用料収入については課税対象である収入となる。 X 適切でない。 組合員から徴収する場合なら、収益事業に該当せず法人税の課税対象とならない。 平成27年 マンション管理士 「問35」 、平成26年 管理業務主任者試験 「問16」 、 平成24年 マンション管理士試験 「問34」 、平成23年 管理業務主任者試験 「問16」 、 平成22年 管理業務主任者試験 「問16」 、 平成19年 管理業務主任者試験 「問16」 など。 税は管理業務主任者試験で出題が多い個所です。 設問の解説の前に、法人化されていないマンションの管理組合という区分所有者の団体の扱い方は、民法上でも明確でないために、過去の判例(最高裁:昭和39年10月15日)によって、「法人格のない社団・財団」とか「権利能力のない社団・財団」と呼ばれることになります。 この詳細は、「マンション管理士 香川事務所」が無料で提供しています、「超解説 区分所有法」の第3条にありますから、参考にしてください。 そこで、税法においても、法人でない管理組合から徴収できるのかどうかで、その扱いを明確に決めておく必要があります。 まず、法人税法では、法人税法第2条8号 「(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 (以下、略)」 とあり、 法人化されていないマンションの管理組合は、「人格のない社団等」として扱われます。 すると、納税義務者として法人税を納めるのは、法人税法第4条1項 「第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 (以下、略)」 とあり、 人格のない社団等に該当する法人化されていないマンションの管理組合は、収益事業を行う場合なら、法人税を納める義務がありますが、その他なら法人税を納める義務はないとなります。 では、次に収益事業とは何かの判断が難しく、これは、もう税務署に聞かないと分かりません。 これは、駐車場の使用料についてですが、平成24年2月3日付で国土交通省住宅局長が国税庁に聞いたところ、回答がありました。この質問内容は複雑ですが、 マンションの管理組合で、駐車場使用料と収益事業の関係は、、 ①組合員のみが駐車場使用料を納める場合...収益事業に該当しない。 ②駐車場の使用において、組合員と外部使用者を区別しないで募集する...全体が収益事業の駐車場業に該当する。 ③駐車場の使用において、まず組合員の使用を優先して募集し、空きがでれば、外部使用者にも募集をかける...組合員の使用については、管理業務の一環としての「共済的事業」であり、収益事業たる「駐車場業」には該当しない。しかし、外部使用者部分については、収益事業の駐車場業に該当する。 と認定されました。 そこで、法人税法上、人格のない社団である管理組合においても、組合員から徴収する専用使用料収入については課税対象である収入となりませんから、課税対象である収入となるは、適切ではありません。 注:どうしてこの設問では、駐車場使用料としないで、専用使用料としてあるのか疑念はあるが、どこかに、国税庁の判断基準が発表されているのかも? NETで調べたが、分からない。 2017年 2月21日追記:どこかに、根拠があったと思って調べると、やはり駐車場使用料はあるが、専用使用料と限っていない。 国家試験での出題なら、幅の広い「専用使用料」ではなく、ここは、明確な国税庁の回答としてある、「駐車場使用料」に限定すべきだ! 他の参考判断:国税庁のホームページより。 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定 これによりますと、 【照会要旨】 団地管理組合又は団地管理組合法人(以下「管理組合」といいます。)が、その業務の一環として、その区分所有者(入居者)を対象として行っている駐車場業は、収益事業に該当するでしょうか。 (事業の概要) 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。 駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。 その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。 駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。 【回答要旨】 照会の事実関係を前提とする限り、収益事業に該当しません。 (理由) 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。 その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。 (注) 団地管理組合…………人格のない社団等 団地管理組合法人……法人税法第2条第6号の公益法人等とみなされます。ただし、寄附金、法人税率については、普通法人と同様に取り扱われます(建物の区分所有等に関する法律第47条第13項)。」 とあり、 法人税法上、人格のない社団である管理組合においても、組合員から徴収する専用使用料収入については課税対象である収入とはなりませんから、適切ではありません。 2 消費税法上、管理組合が共用部分である駐車場を有償で使用させる場合、使用者が組合員であっても使用料は課税の対象となる。 X 適切でない。 マンションの駐車場使用料は、組合員が使用するなら、消費税は不課税となる。 平成26年 管理業務主任者試験 「問16」 、 平成23年管理業務主任者試験 「問16」、 平成22年管理業務主任者試験 「問16」、平成18年管理業務主任者試験 「問16」、平成16年管理業務主任者試験 「問16」。 選択肢1の法人税と異なり今度は、消費税での設問です。 この回答は、国税庁のQ&Aより、(消費税法第2条第1項第8号) 「マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。 イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。 ロ 管理費等の収受………不課税となります。」 とあり、 消費税法上、管理組合が共用部分である駐車場を有償で使用させる場合、使用者が組合員であれば、使用料は課税の対象となりませんから、適切ではありません。 3 消費税法上、管理組合が金融機関から借入れをした場合に生じる借入金の利子は課税取引であり消費税の課税対象となる。 X 適切でない。 消費税法上、預貯金や貸付金の利子は、非課税である。 多くの項目で消費税が課税されるかどうかは、判断が難しいので、具体的には、税務署の判断基準があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6221.htm それによると、 「消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。 具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。 1 預貯金や貸付金の利子 」 とあり、 利息には、消費税は課税されませんから、誤りです。 なお、弁済金の元金部分は、不課税取引に該当して消費税は課税されません。 4 消費税法上、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、特定期間の課税売上高によっては、消費税の納税義務が免除されない場合がある。 〇 適切である。 特定期間の制度が改正で追加された。 まず、課税売上高とは、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。 そして、消費税法の基準期間は、消費税法第2条1項14号 「十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。 」 とあり、 基準期間は、原則、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人の場合は原則として前々事業年度のことをいいます。 そして、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。 消費税法第9条 「(小規模事業者に係る納税義務の免除) 第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (以下、略)」 とあり、 原則:2年前の課税売上額が、1,000万円を超えると、2年後には、納税の義務があるという、通常なら、税は翌年が対象なのに、他と比べて、おかしな制度です。 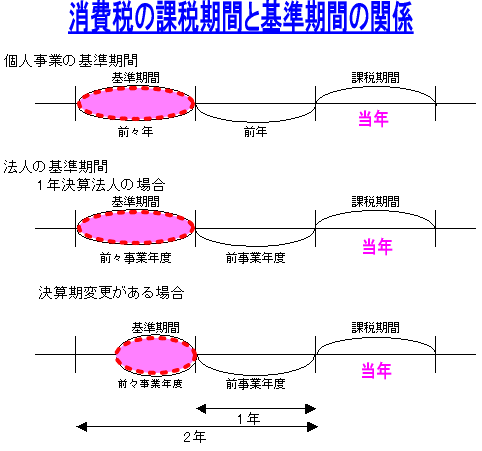 この消費税法では原則:前々年が基準期間となっているため、資本金1,000万円未満の新設法人では基準期間の課税売上額がないことを悪用して、新設法人の設立事業年度と翌事業年度に売り上げを計上して消費税を逃れ、設立3年目には廃業するという事態が多く発生しました。 そこで、平成23年6月の消費税の改正で、特定期間という制度を新しく設けました。 それが、消費税法第9条の2 「(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例) 第九条の二 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。 (以下、略)」 とあり、 特定期間は、具体的には、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。消費税法第9条の2 4項) 改正前の2年後から消費税を納める期間を早めています。  特定期間の計算例 ・個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間ですので、例えば、事業を行っていない個人の方が3月1日に開業した場合には、3月1日から6月30日までの期間の課税売上高(又は給与等支払額)で判定することとなります。 また、その前年7月1日から12月31日までの間に開業した場合には、特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)がないため判定不要です。 そこで、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となりますから、適切です。 香川注:平成23年6月で消費税が改正された訳ですが、これも判定や前々年との関係において制度が分かり難くて不評です。 答え:4 《タグ》税。 法人税。消費税。 管理組合での課税・非課税。 基準期間と課税期間。特定期間の創設。 特定期間の図を作成するために、時間がかかった。過去問題をやっていれば、選択肢4は知らなくても、選択肢1~3は不適切と分かる。 *ある受験生の感想:選択肢4に関しては「場合がある」とかいう言い回しは大抵その可能性が1%でもある時を指してる気がして選択肢4にした。 |
|
[問 17] 建ぺい率、容積率などに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。 |
|
[問 18] マンションの廊下及び屋内階段に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、正しいものはどれか。なお、避難上の安全の検証は行わず、国土交通大臣が定めた構造方法については考慮しないものとする。
とあり、
とあり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[問 19] エレベーターの安全装置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
|
[問 20] マンションの屋上、バルコニー等の防水に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
|
[問 21] 次の記述のうち、水道法及び「水質基準に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。 |
|
[問 22] 共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
|
|
[問 23] 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に示された建築物の耐震診断の指針(以下、本問において「本指針」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
|
|
[問 24] 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度における新築住宅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
|
[問 25] 消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全点検制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
|
ここまで、問25 |
2017年 2月21日:再度見直した。
2017年 1月27日:第1稿Up。時間がかかる!
解説開始:2016年12月12日